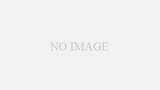親が高齢者施設に入る話が具体的になると、「住んでいた家をどうするか」が大きな課題になります。
売る?貸す?そのまま保有?──そこで鍵になるのが「名義」です。
認知症になる前に、家族信託を活用して名義や管理の準備をしておくと、後々の選択肢が大きく広がります。
今回はその具体例をご紹介します。
施設入所後の「空き家問題」は早めに備える
親が施設に入ると、住んでいた家は空き家になります。
ところが、名義が親のままで、しかも認知症が進んでしまうと、売却や賃貸などの手続きができなくなるのです。
空き家のままでは固定資産税もかかり続け、防犯や老朽化のリスクも増します。
こうした事態を避けるために、家族信託を使って子どもが家を管理できるようにしておくことが有効です。
家族信託なら、名義を変えずに管理できる
家族信託の特徴は、「名義を変えずに管理権限を渡せる」ことです。
信託契約によって、親の名義のままでも、子どもが売却や賃貸などの判断と実行ができるようになります。
たとえば、「母が施設に入るときに家を売り、その資金で入居費用をまかないたい」といったケースでは、母が元気なうちに家族信託契約を結んでおけば、スムーズに売却できます。
実際のご相談例
認知症が進行してしまった後のケース
「父が入院し、その後施設へ入ることになったが、家の名義がそのまま。父は既に認知症が進んでおり、どうにも動かせない」
こうした相談は非常に多く、成年後見制度を使うと裁判所の監督が必要になり、家を売るのも一苦労です。
信託契約があればスムーズに対応
しかし、事前に家族信託契約を結んでおけば、子どもが「受託者」として家の売却を行えます。
親の介護や施設費用の準備にとって、大きな違いになります。
親の意思確認ができるうちに準備を
家族信託は「契約」ですので、親の判断力がしっかりしているうちにしか結べません。これが最大のポイントです。
「そのうちやろう」と思っていたら、気づけば認知症が進行して契約できなくなった……というケースも多いのです。
ですから、施設入所や介護が見えてきた段階で、早めに準備をしておくことが安心につながります。
司法書士に依頼するメリットとデメリット
家族信託の設計には、法律と実務の知識が必要です。契約の内容を間違えると、いざというときに思った通りの対応ができないこともあります。
司法書士に依頼することで、そうしたリスクを減らし、目的に合った契約を作ることができます。ただし、専門家への依頼には費用がかかるため、その点がデメリットになるかもしれません。
とはいえ、資産が動かせなくなるリスクに比べれば、小さなコストだと言えます。
当事務所では、丁寧なヒアリングをもとに、最適な家族信託をご提案しています。ご興味があれば、ぜひご相談ください。