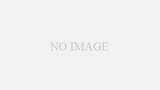認知症になると、本人の口座は原則家族でも動かせず、生活費や医療費の支払いが滞るおそれがあります。
理由は、銀行は本人確認ができない取引を止める決まりだからです。
対策は、法定後見や家族信託などを元気なうちに準備すること。私は司法書士として、ご家庭の事情に合わせた現実的な備えをご提案します。
預金は本人しか引き出せない仕組み
銀行口座は名義人の意思確認が前提で動きます。
認知症で判断力が低下すると、窓口や書面での意思確認ができず、金融機関は安全のため取引を停止します。
家族名義のキャッシュカードでも引き出しは不可。
しかし、日々の支払いは待ってくれません。ここで「家族なのにどうして?」という声をよく伺いますが、家族といえど別人格という民法の考え方に基づくためです。
口座凍結は冷たい対応ではなく、本人財産を守るための防波堤だと理解しておきましょう。
生活費や医療費が払えない深刻さ
施設費や介護サービス費、入院時の自己負担などは毎月の固定出費。
凍結が長引けば、ご家族の立替やカードローンに頼る事態にもなりかねません。
また、固定資産税・保険料・公共料金などの口座振替も止まります。
延滞が続けば信用情報に影響することも。
特に、配偶者の年金だけでは足りないご家庭では、数か月で資金繰りが苦しくなるケースが珍しくありません。
小さな遅れが重なり、家族全体の負担が一気に増える点が要注意です。
法定後見制度で対応できるが課題もある
すでに凍結された後に動かすには、家庭裁判所で成年後見人を選んでもらう方法があります。
選任されれば、預金の管理・支払いは可能。
しかし、柔軟な資産移動がしづらい(たとえば自宅売却や大口の贈与は裁判所の許可が必要)、毎年の報告義務や専門職後見人が付く場合の継続費用など、運用面の負担があります。
加えて、申立から開始までに一定の期間を要するため、今すぐ支払いが必要という場面では間に合わないこともあります。
家族信託という柔軟な備え方
元気なうちに契約を結び、信頼できる家族に財産管理を任せるのが家族信託。
受託者(任された家族)が契約に沿って口座の支払い・資産の組み替えを行えるため、認知症発症後も支払いを止めない設計ができます。
また、裁判所の関与は原則不要で、生活費・医療費・施設費などの支出基準を事前に細かく決められます。
特に、不動産の売却や賃貸化など、将来の資金計画に柔軟性を持たせたいご家庭には相性が良い方法です。
いつ動く?準備のタイミングと手順
タイミングは「元気な今」が最適です。
手順は
①現状整理(資産・収支・希望)
②設計(誰に何を任せるか)
③契約書作成
④口座・不動産などの実務手続。
また、受託者は実務を担える人を選ぶのがコツ。
二人以上で役割分担(長男は入出金、長女は記帳確認など)にすると、チェック体制も強化できます。
私は面談で支出の優先順位を一緒に決め、無理のない運用ルールに落とし込みます。
こういう家庭は特に要注意(事例)
不動産はあるが預金が少ない
自宅や貸家はあるが手元資金が乏しいケース。
売却や賃貸への切替を計画に入れておかないと、いざという時の支払いが続きません。
家族が遠方・単身世帯
窓口対応や書類手続の遅れが致命傷になりがち。
受託者を複数にしておくと安心です。
二次相続も見据えたい
配偶者の介護と次世代への承継が交錯。
受益者連続型の設計で「配偶者→子」へと支払いと承継を滑らかに。
費用感と期間の目安
家族信託は設計の深さで費用が変わりますが、単純な金銭信託と不動産を含む信託では手続の量に差があります。
期間は、ヒアリングから契約までおおむね数週間~数か月が目安。
法定後見は申立から開始まで数週間以上を見込む必要があります。
どちらが良いかは、ご家族の体制・資産の種類・求める柔軟性で変わりますので、個別設計が肝心です。
認知症で口座が凍結すると、生活費や医療費の支払いがすぐに詰まり、ご家族の負担は一気に増えます。
司法書士に依頼するメリットは、法律と実務の両面から設計し、止めない支払いを現実的に実装できること。
制度の選択や契約書の精度、手続の順番まで伴走します。
一方のデメリットは、費用がかかること、面談や資料準備に時間をいただくことです。
それでも、凍結後に慌てるより今の準備が家族の安心を守る最短ルートです。
当事務所なら事情に合わせた最適解をご提案できます。まずは現状ヒアリングから、気軽にご相談ください。